行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
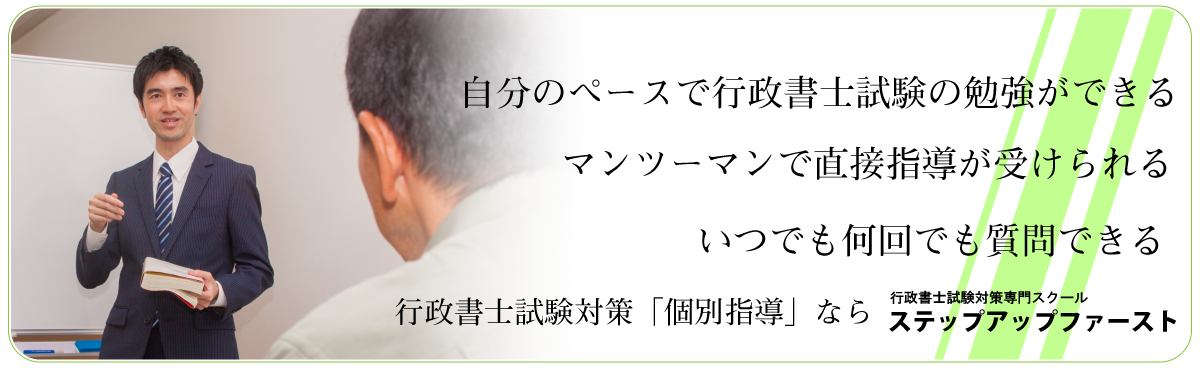
令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
問題3 憲法・人格権と夫婦同氏制 正解「5」
1【妥当】(最判昭63.2.16)<初出題>
選択肢の通り。
氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別して特定する機能があるけど、同時に、個人からみれば、人が個人として尊重される基礎で、個人の人格の象徴で、人格権の一内容を構成するもの、という判例があります。
2【妥当】(最大判平27.12.16)<初出題>
選択肢の通り。
氏(名字)は、婚姻・家族に関する法制度の一部として法律が具体的な内容を決めているものだから、氏に関する人格権の内容も、憲法で1つに決められているものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度によって、初めて具体的に捉えられる(決められる)、という判例があります。
3【妥当】(最大判平27.12.16)<初出題>
選択肢の通り。
家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位だから、氏(名字)をその個人の属する集団を想起させるものとして一つに定めることにも合理性がある、という判例があります。
氏が、親子関係など一定の身分関係を反映して、婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されている、という判例もあります。
4【妥当】(最大判平27.12.16)<初出題>
選択肢の通り。
現行の法制度の下での氏(名字)の性質を考えると、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない(氏の変更を強制されない自由は、人格権の内容ではない)、という判例があります。
5【妥当でない】(最大判令3.6.23)<初出題>
「憲法上保障される人格権の一内容とはいえず、当該利益を婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討する際に考慮するか否かは、専ら立法裁量の問題である」が×。
「憲法上保障されるかどうかはともかく、個人の重要な人格的利益といえる」にすると〇。
婚姻の際に氏(名字)を改めることは、婚姻の前後を通じた信用や評価を著しく損なうだけでなく、個人の人格の象徴を喪失する感情をもたらすなど、重大な不利益を生じる可能性があることは明らか。
したがって、婚姻の際に婚姻前の氏を維持することに関する利益は、憲法上の権利として保障されるかどうかはともかく、個人の重要な人格的利益ということができる、という判例があるので、婚姻前に築いた個人の信用などを婚姻後も維持する利益は、憲法で保障される人格権の内容の1つではない、という判断はしていなくて、憲法で保障されるかどうかはともかく、個人の重要な人格的利益だ、と判断しています。
行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
人気教材ランキング(オンラインショップ)
代表者(講師)
お問い合わせ
スクール外観
駐車場
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。







