行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
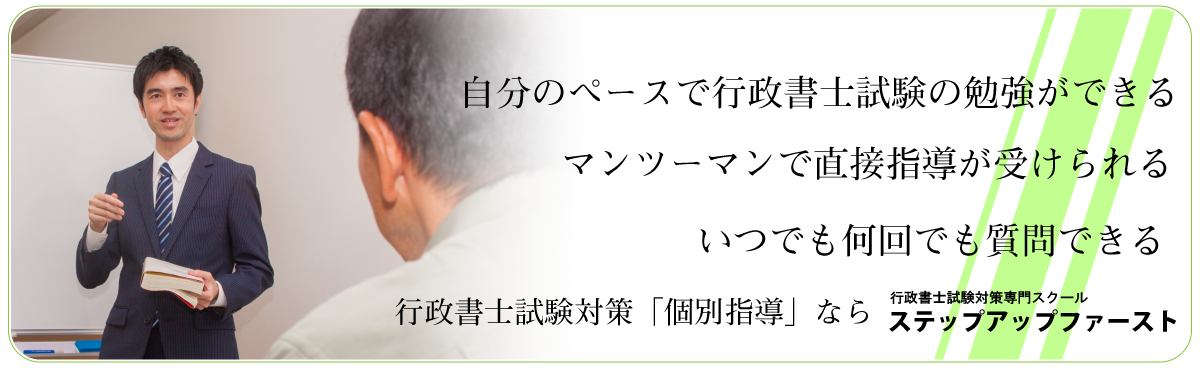
平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)
問題1 基礎法学・第二次世界大戦後の日本の法制度 正解「4」
前回(平成25年度)に引き続き、受験生の戦意喪失を狙った1問目。
この問題を見て「そんなの知らないよ?!」と思考停止してしまった人は、冷静さを欠いてこの後の問題の正解率に影響が出てしまったと思います。
逆に、「はいはい、捨て問乙乙(おつおつ)」と飛ばせた人は、この後もいつも通りに解けたのではないでしょうか。
各出来事の年数を知っていればもちろん解けますが、知らなくても正解率を50%まで高めることはできた問題です。
年代順になっている1~5を眺めると、最後は「ウ」か「オ」になっています。
ウ(環境基本法の制定)とオ(裁判員制度の導入)なら、裁判員制度の導入の方が後かな?と考えることはできたのではないかと思います。
「環境基本法の制定」はなじみがないかもしれませんが、「裁判員制度の導入」はニュースなどでそれなりに耳にしていたでしょう。
そうすると、正解は「2」か「3」か「4」に絞られます。
次に、2~4の後ろから2・3番目を見ると、「エ⇒ウ」か「ウ⇒エ」になっています。
ウ(環境基本法の制定)とエ(成年後見制度の創設)は、どちらが後か。
簡単ではありませんが、「成年後見は割と新しい制度」というイメージがあれば、「ウ⇒エ」の方が正しい可能性が高いかな、と判断できたのではないでしょうか。
また、「ウ⇒エ」は2つあるので、より正しい可能性が高いという判断もできます。
そうすると、正解は「3」か「4」に絞られます。
後は、勘が冴えていることを祈るだけです。
「行政事件訴訟法ができたのと、家庭裁判所ができたのは、家庭裁判所ができた方が先っぽい」と思って4にした人は、お見事!。
ちなみに、各出来事の年は次の通りです。
実は、アとイの順番が逆なだけで、後は年代順に並んでいました。
ア:行政事件訴訟法の創設 ⇒ 1962年
イ:家庭裁判所の創設 ⇒ 1948年
ウ:環境基本法の制定 ⇒ 1993年
エ:成年後見制度の創設 ⇒ 1999~2000年
オ:裁判員制度の導入 ⇒ 2004~2009年
行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
人気教材ランキング(オンラインショップ)
代表者(講師)
お問い合わせ
スクール外観
駐車場
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。







