行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
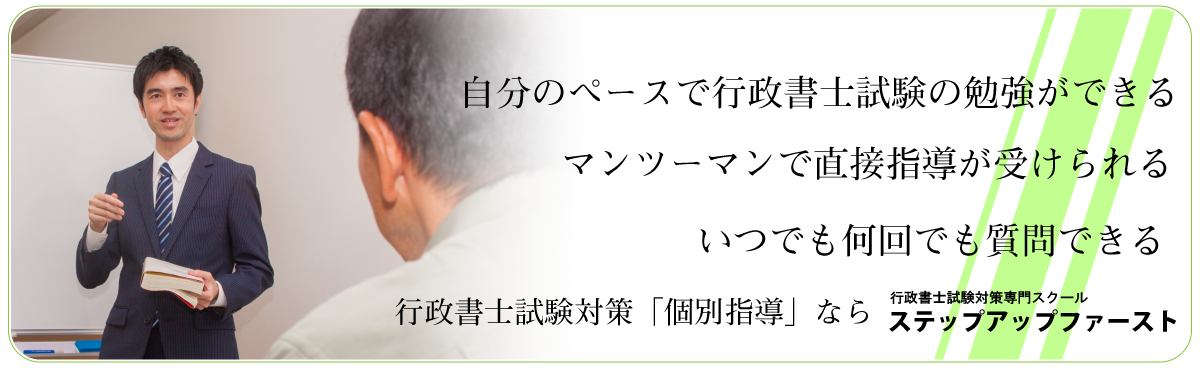
令和6年度(行政書士試験 過去問の解説)
問題41 憲法・婚外子の法定相続分
正解「ア⇒8、イ⇒2、ウ⇒4、エ⇒10」
(最大決平25.9.4)からの出題。
ア【8:先例】<初出題>
イ【2:事実上の拘束性】<初出題>
どちらもノーヒントなので、難しい空欄です。
裁判所が、ある問題(争点)について判断を下した後で、他の裁判で同じことが争われた場合、前に下された裁判所の判断に従わなければならない、という原理のことを先例拘束性の原理といいます。
この原理を知っていたら、空欄アには「先例」、空欄イには「事実上の拘束性」が入ると判断できましたが、先例拘束性の原理は、これまで出題されたことのない内容なので、初見で正解するのは難しかったです。
ウ【4:法的安定性】<初出題>
最初の空欄ウを含む文章「いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく【ウ】を害することになる」がヒント。
解決済みの事案(遺産分割が終わっている事案)にも、今回の判例の効力が及ぶことになると、遺産分割をやり直すことになるケースが出てくると考えられます。
せっかく終わった遺産分割が、やり直しになることで害されることになる語句としては「4:法的安定性」「12:家族法秩序」あたりが候補になりますが、その後の文章で「【ウ】は法に内在する普遍的な要請」とあるので、対象が家族法に限定されている「家族法秩序」よりも、「法的安定性」の方が普遍的な要請という内容にふさわしいと考えることができたら、空欄ウには「法的安定性」が入ると判断できました。
エ【10:確定的】<初出題>
2段落目「既に関係者間において裁判、合意等により【エ】なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではない」がヒント。
既に裁判などで【エ】になった法律関係を、この判例で覆すのはふさわしくない、という意味になるので、裁判は、法律関係を「確定」させるためにするものだと連想できれば、空欄エには「確定的」が入ると判断できます。
行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
人気教材ランキング(オンラインショップ)
代表者(講師)
お問い合わせ
スクール外観
駐車場
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。







